最初の相談から手続きの完了まで、担当者が変わることなく、同じ女性行政書士がしっかりサポートいたします。
どうぞ安心してご相談ください。
離婚協議書や離婚公正証書を作成するとき、「養育費の支払い期間」をどう設定するかは、多くの方が悩むポイントです。
「成人するまで?」「大学卒業まで?」など、状況や考え方によって意見が分かれる部分です。
今回は、一般的な設定方法や注意点をまとめます。
1. 養育費の支払期間は「子どもが何歳になるまで」?
養育費は、法律上は親権者である親が、未成年の子どもを扶養するために必要なお金です。
そのため、支払い期間は「成人するまで(満18歳または満20歳)」とされることが多いです。
最近の成人年齢変更
2022年4月から、民法上の成人年齢は18歳になりました。
ただし、高校在学中の生活費や学費負担を考慮し、「高校卒業の年度末(満18歳3月まで)」や「満20歳まで」とするケースもあります。
2. 高校卒業後の進学を考慮する場合
子どもが大学や専門学校に進学する可能性が高い場合は、**「満22歳に達した年度末まで」**とすることもあります。
これは進学による生活費や学費負担をカバーするためです。
ただし、進学を条件にする場合は、「進学しない場合は〇歳まで」と明記しておくとトラブル防止になります。
3. 期間を決めるときの注意点
- あいまいな表現は避ける(例:「成人するまで」ではなく「満18歳に達した年度末まで」など明確に書く)
- 複数の子どもがいる場合は、それぞれの年齢や支払期間を明記する
- 物価や生活状況の変化に備えて、将来の見直し条項を入れておくと安心
4. まとめ
- 一般的には「満18歳の年度末まで」が多いが、進学を考慮して「満22歳年度末まで」とすることもある
- 期間や条件はできるだけ明確に記載
- 将来の見直しができるよう、柔軟な条項を入れておくとトラブル防止になる
離婚協議書や離婚公正証書の作成では、このようにちょっとした文言の違いが将来の大きな差につながることがあります。
当事務所では、養育費・面会交流・財産分与など、将来のトラブルを防ぐための文案作成をサポートしています。
最初の相談から手続きの完了まで、担当者が変わることなく、同じ女性行政書士がしっかりサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。


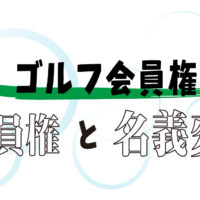



この記事へのコメントはありません。